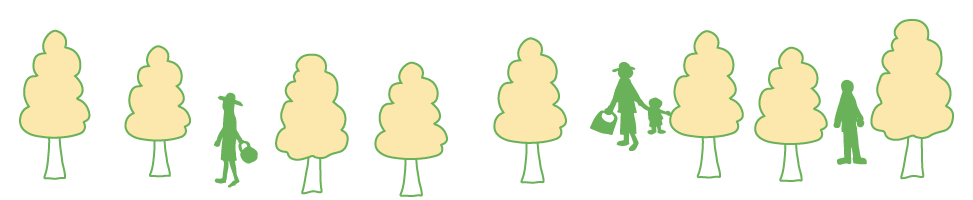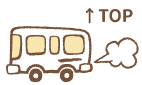中区障害者基幹相談支援センター
児童部会(令和4年度)
令和元年4月に中区単独の児童部会を立ち上げました。
障害のある子どもが地域で安心して暮らせるまちづくりを目的に児童関係機関が集まり、学習会や見学会を行っています。

専門部会の協議で見えてきた課題等
(2)相談支援専門員との連携
| 現状・課題 | ◆セルフプランの方が多いこともあり、相談支援専門員と連携する機会が少ない | |
| 現状・課題に対する意見 | ◆できれば、相談支援専門員には定期的に部会へ参加して欲しい | |
| 解決に向けた取り組み (対策) |
【中央療育センターに対して、児童部会への参加協力を依頼】 アンケート結果から「子どものライフステージに合わせて、その都度相談できるようしたい」「子どものことについて気軽に相談できるようにしたい」「子どもの支援方法について共有したい」とのニーズを確認
中央療育センターへ児童部会への参加協力を依頼し、令和4年度から児童部会へ参加することとなった |
(1)教育関係機関とのネットワークの構築
| 現状・課題 | ◆利用者に関わる学校との連携が難しい | |||
| 現状・課題に対する意見 | ◆学校との情報共有・顔の見える関係づくりができていない ◆学校と支援の方向性が確認できていない ◆学校に地域の事業所を知ってもらう機会がない ◆学校とどんな関係をつくりたいのか、事業所が何に困っているのか把握できていない ◆事業所の困りごと、ニーズを再確認する必要があるのではないか |
|||
| 解決に向けた取り組み (対策) |
【部会員に対するニーズの再確認】 部会員への聞き取りアンケートを実施。「地域でのチーム支援・統一した支援がしたい」「学校と足並みを揃えた支援がしたい」「学校と困りごと・うまくいったことの共有がしたい」といったニーズを再確認した
【学校との関係づくりのために「福祉教育連絡会」「福祉体験プログラム」に参加
地域の資源を活用したネットワークの在り方について検証する機会となった
現在実践している情報を共有することで、個々の事業所ごとでの学校との関係づくりについて考える機会となった |
活動報告
第6回 児童部会
| 開催日時・場所 |
令和5年3月10日(金)10:30~12:00 ZOOM開催 |
|---|---|
| 出席者 |
14機関18名 |
| 内容 |
(1)「保育所等訪問支援について実践から学ぶ」 ①保育所等訪問支援とは 保育所等訪問支援について、中区基幹センター鎌田より資料をもとに概要を説明 ②実施事業所からの報告 ・LITALICOジュニア名古屋伏見教室(間瀬) ・ドリームズ21st(鈴木) それぞれ報告をいただき、参加事業所からの質疑応答を行なう。 (2)各事業所自己紹介 各事業所自己紹介および、報告会の感想をいただく (3)令和5年度年間計画について 令和5年度年間計画予定表をもとに活動内容について確認を行なう (4)その他 令和5年度部会長紹介 ※後日報告について部会アンケート実施 |
第5回 児童部会
| 開催日時・場所 |
令和5年2月22日(水)10:30~12:00 イーブルなごや3階大研修室開催 |
|---|---|
| 出席者 |
8機関10名 |
| 内容 |
(1)部会長挨拶 (2)新規事業所紹介 (3)令和4年度振り返りについて ※令和4年度の活動内容について、実施した内容ごとに成果を確認した。 ①グループワーク(第2回) 内容:「福祉教育連絡会」「学校との交流会」で具体的な関り方や、「事例検討会」で行ないたい事例を考える。 評価:△(必要に応じて今後も実施する) ②事例報告(第3回部会) 内容:成功事例の共有 ・「学校との環境設定」リオフレンド 渡辺氏 ・「連携会議の設定」K-YsStyle東別院 川村氏 ・「保育所等訪問支援」LITALICOジュニア名古屋伏見教室 間瀬氏 評価:〇 ③福祉体験プログラム(令和4年度福祉体験プログラム参加表をものに確認) 内容:・老松小(11月22日打ち合わせ 12月8日実施)(手話体験) ・名城小(12月13日打ち合わせ 1月17日実施)(聴覚障害者とボッチャ) ・大須小(12月16日打ち合わせ 1月24日実施)(ボッチャ) 評価:〇 参加事業所が少なく学校との連携に効果があるかは検証しきれていないため、来年度も効果を検証するために継続。 ④福祉教育連絡会 内容:視覚障害のある方への対応について 児童部会活動説明、中区内児童関係事業所紹介 評価:〇 (4)令和5年度年間予定について 下記4点については、令和5年度も継続して取り組む ①事例検討会 ②福祉体験プログラム ③福祉教育連絡会 ④教員との交流会 (5)その他 |
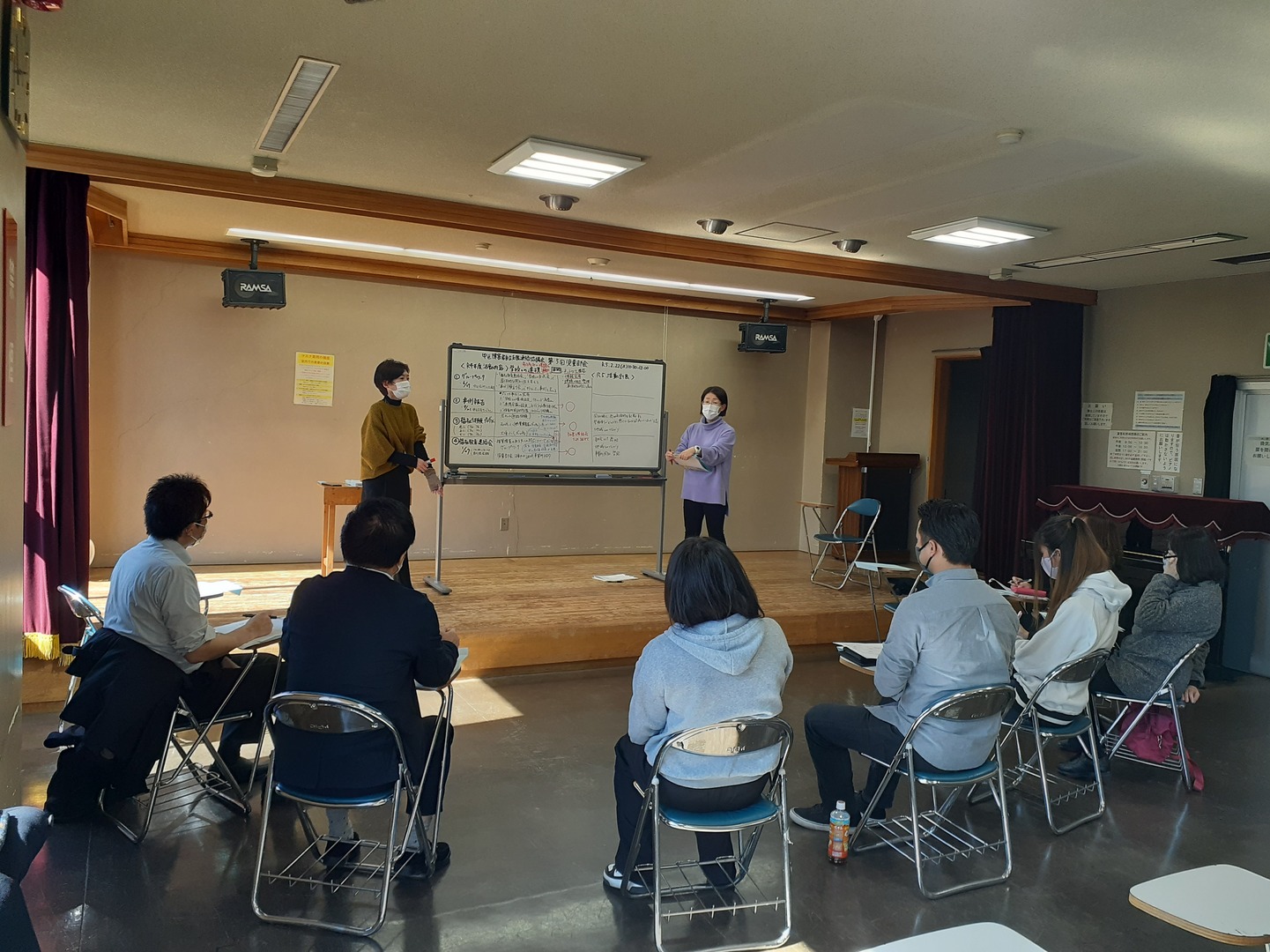
第4回 児童部会
| 開催日時・場所 |
令和5年1月27日(金)14:00~16:30 東別院会館 2階201蓮開催 |
|---|---|
| 出席者 |
6機関7名 |
| 内容 |
(1)講演「視覚障害について」 講師:寺西美予氏(名古屋ライトハウス情報文化センター職員) 盲導犬:ファミーユ ・資料に基づき、視覚障害者の日常生活の困難さや対応策について、また盲導犬についての説明がある。 (2)視覚障害者あるある寸劇 ・中社協の職員と寺西氏により、日常生活の一場面を再現。始めに悪いパターンを行ない、それを見た後でグループにてどうすればよいかを話し合い、グループの代表に良いと思われるパターンをやってもらう。 (3)質疑応答 (4)中区障害者基幹相談支援センターより (5)社協アンケート記入、事務連絡 |
第3回 児童部会
| 開催日時・場所 |
令和4年11月30日(水)10:30~12:00 イーブルなごや2階視聴覚室開催 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 出席者 |
11機関14名 |
|||
| 内容 |
(1)部会長LITALICOジュニア名古屋伏見 森 英晴氏より開催の挨拶 (2)事例検討会について(中区基幹センター鎌田より) ・本日の進め方を説明 ・グループワークの目的を確認 ⇒事例から今後の支援に活かせるポイントを持ち帰る。 思考、支援の幅を広げる。 (3)事例検討会「学校との連携~連携がうまくいったケースについて~」 ※事例3ケースを全体で共有し、一つの発表毎に質疑応答を行なう ・ケース概要10分 ・質疑応答 12分 ・まとめ 3分 計25分 【事例3ケース】
|

福祉体験プログラム(大須小学校)
| 開催日時・場所 |
令和5年1月24日(火)13:25~15:00 東別院会館 2階201蓮開催 |
|---|---|
| 出席者 |
3機関3名 |
| 内容 |
ボッチャ交流会(障害者(身体障害・聴覚障害・視覚障害・高次脳機能障害・脳性まひ))と6年生児童による交流) ・福祉体験プログラムに福祉学習サポーターとして参加する。グループに分かれ、チーム内で一緒にボッチャをしながら児童と障害当事者とのやり取りの補助を行なう。 ①講師紹介 ②障害者1名を含め5グループに分かれて座り、自己紹介をし、リーダーとチーム、投げる順番を決める。 ③ 5グループの総当たり戦 ④ ゲーム終了後、各講師からの感想 ⑤ 質疑応答 ⑥教員からのまとめ |
福祉体験プログラム(名城小学校)
| 開催日時・場所 |
令和5年1月17日(火)9:35~11:20 名城小学校体育館および会議室開催 |
|---|---|
| 出席者 |
2機関2名 |
| 内容 |
聴覚障害者とのボッチャ交流(ひまわりの会と5年生児童による交流) ・福祉体験プログラムに福祉学習サポーターとして参加する。グループに分かれ、チーム内で一緒にボッチャをしながら児童と聴覚障害当事者とのやり取りの補助を行なう。 ① ひまわりの会紹介 ②各グループで集まり、それぞれ自己紹介とチーム名を決める。 ③5グループでの総当たり戦。ゲームをやっているチームに当事者が交代で入り一緒に行なう。 ④全ゲーム終了後、会議室へ移動。当事者からの話し。 ⑤質疑応答 ⑥各グループの代表児童からの感想 |
福祉体験プログラム(老松小学校)
| 開催日時・場所 |
令和4年12月8日(木)10:40~12:15 名城小学校体育館および会議室開催 |
|---|---|
| 出席者 |
3機関3名 |
| 内容 |
手話体験(ひまわりの会と3年生児童による交流) ・福祉体験プログラムに福祉学習サポーターとして参加する。グループに分かれ、その中で児童と聴覚障害当事者とのやり取りの補助を行なう。 ①ひまわりの会、福祉学習サポーターの自己紹介 ②ひまわりの会当事者より講和(覚えてほしい手話、日常生活での困りごとについて) ③日常生活用具・手話以外コミュニケーション方法紹介(パトライト、耳のマーク、読み取りアプリなどについての紹介) ④手話体験(グループに分かれ、それぞれお題のイラストを見てどう表現するか話し合い、当事者に見てもらい、何かを当ててもらう) ⑤手話体験(グループに分かれ、当事者が入り手話で自己紹介(名前、好きな物など)をできるようにする。 ⑥ それぞれのグループから感想を発表。 ⑦質問タイム |
第2回 児童部会
| 開催日時・場所 |
令和4年9月21日(水)10:30~12:00 中区役所6階大会議室1開催 |
|---|---|
| 出席者 |
15機関18名 |
| 内容 |
(1)部会長LITALICOジュニア伏見 森 英晴氏より開催の挨拶 (2)グループごとに事項紹介と役割決め ・自己紹介 ・司会、書記、発表者を決める (3)グループワークについて(中区基幹センター鎌田より) ・本日の進め方を説明 ・グループワークの目的を確認 ⇒今年度の目標「地域での統一した支援」「学校との足並みを揃えた支援」を行なうために、①福祉教育連絡会 ②学校との交流会 ③事例検討会 において、具体的に何ができるのかをアイデアを出し合い考える。 (4)グループワーク「学校との関係づくりについて~具体的なアプローチを考えよう~」 【グループワーク内容】 ① 福祉教育連絡会(1月開催予定・中区社会福祉協議会主催)の場で何ができるか? ② 学校との交流会(来年度に向けて)どのような場にしたいか? ③ 事例検討会でどのような事例をやりたいか? ※各ワークの前にそれぞれのワークの趣旨や目的の説明を行なう(基幹センター鎌田より) ※①~③それぞれ、個人ワーク(3分)グループワーク(10分)まとめ(5分)を行なう (5)グループ発表 ・1グループ3分で発表 (6)部会長LITALICOジュニア伏見 森 英晴氏より閉会の挨拶 (7)その他 ・アンケートについては後日メールまたはFAXで送付するため、回答への協力を依頼する |


第1回 児童部会
| 開催日時・場所 |
令和4年6月27日(木)10:30~12:00 イーブル名古屋第4集会室開催 |
|---|---|
| 出席者 |
13機関15名 |
| 内容 |
(1)自己紹介と部会長について ・部会長 ⇒LITALICOジュニア名古屋伏見 森 英晴様 任期1年 開所順に輪番制 (2)令和3年度の活動振り返り ・学校とどんな関係をつくりたいのか、事業所が何に困っているのか把握できていない ・事業所の困りごと、ニーズを再確認する必要があるのではないか ⇒ 部会員への聞き取りアンケートを実施(6月) (3)アンケート集計結果と今後の活動について(別添資料⑤参照) 【アンケート集計結果より3r抽出されたニーズ・目的】 ・地域でのチーム支援・統一した支援 ・学校と足並みを揃えた支援 ・困りごと、うまくいったことの共有 ⇒ アンケート結果をもとに、福祉教育連絡会と福祉体験プログラムへの関わり方について中区社会福祉協議会(飯田氏)と確認し協力を依頼 【今後の活動について】 ① 福祉教育連絡会には児童部会として参加し、地域の方・学校関係者と積極的に関わりを持つ ② 福祉体験プログラムに参加を希望する事業所は、事務局まで参加希望表を送付する ③学校・教員との交流会については、来年度開催に向けて準備を進める。その準備として関わりのある学校の先生などから協力していただけるかの確認をする。 (4)その他 ・名古屋市自立支援連絡会東ブロックで行なった「障害児支援のアンケート」について |